☆医王寺の庭園について☆
皆さん、こんにちは
では前回に引き続き、『医王寺』に関してご紹介していきたいと思います。
今回は医王寺の庭園について!
医王寺の庭園と言えば美しく、磐田なのに磐田ではないような空間が広がっている特別な場所ですよね。
早速紹介していきたいと思います。
まず、医王寺の庭園は『枯山水』といいます。
枯山水とは、水のない庭に石や白砂を用いて
水の流れを表現した日本庭園のことをさします。
歴史からお話していきますと…
お庭がつくられたのは、江戸時代の元和年間(1620頃)に造園されたそうです。
客殿の西側と南側を合わせて約1,000㎡になります

作者は小堀遠州(こほり えんしゅう)とも、本山京都智積院化主猊下第7世
運敞僧正(うんしょう そうじょう)とも言われ、残念ながら寺伝等に記されているものは
見つかっていないようです。しかし、石組みや作風など、小堀遠州の作庭する庭と
よく似ています。また、小堀遠州の旅行記が医王寺に残っていることからみても、
何らかの関係があったことは確かです。

因みに小堀遠州は 書画・和歌に優れた王朝文化の理念と茶道を結びつけ、
「綺麗さび」という幽玄・有心の茶道を創り上げたようです。
京都の「二条城二の丸庭園」という池泉回遊式を代表する
書院造庭園(武家の邸宅の庭園)を造った方です。
日本を景色を彩る才能というのはとても素敵ですよね
庭園の西から北にかけて築山として、写真の正面より左の一番高いところに、
三尊石組(仏像を三尊仏のように中央に大きな石をその左右に小ぶりな石を置く事)
を据え、その下に枯瀧石組(滝が流れている様子を表現)。
枯流れ護岸石組にして深山の渓谷を表しています。
また、庭園南側は、一面のスギ苔の海の中に石組はあるようなおとなしい構成に
なっています。(苔の見頃が過ぎてしまったので、申し訳ないです )
)
苔の見頃は5月下旬から6月上旬です
西側の築山部分を動的するならば、北側が静の庭であり、対比をなしています。
雪が被ったり、ライトアップされるなどして、様々な見え方で見えるので
季節が変わるごとに通うのも楽しいと思います

そして、庭園全体に目を向けてみると、五群に分けられた石組は、それぞれが
表情を示しております。石組に使用されている石は地元の天竜産の青石を
はじめとして、紀州石の名石も多く使われています。
石のほとんどが建てて組まれていて、静岡県のこの地方に多く残っている、
小堀遠州の庭と同じつくりのようです。
実際に、小堀遠州のつくられた他のお庭と医王寺の庭園を見比べて、
特徴的なところが作品に表れており、「やはり?」と感じることが
多かったです。ここが似ている!と思うのを探しながら拝観するのも
良いかもしれません
また、先日伺った際は紫陽花も綺麗に咲いておりました

とても素敵だったので、お写真を撮りました(^▽^)/
紫陽花も見頃が6月中旬ぐらいになります!敷地内の様々なところに
紫陽花は彩りをましており、とても美しかったので、おすすめです

いかがでしたでしょうか?
実際に拝観するからこそ感じる庭園の魅力に触れてみてほしいですし
拝観の際にお寺にはいるのですが、とても不思議だけど居心地のよい空間でした。
ぜひ、お時間がある際は医王寺に足を運んでみて下さい!
拝観料金
大人:200円 子人:100円
>>アクセス<<
公共交通機関 電車⇒御厨駅 下車後 南口へ 徒歩5分
車は10台ほど止められますが、公共交通機関の方が
個人的はおすすめです。
 nagisa
nagisa





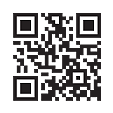

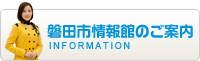


コメントする